固定観念は一度思い込んだら逃れられない
固定観念の英単語を検索すると
Stereotype という単語が表記されました。
ステレオタイプとは、多くの人に浸透している先入観、思い込み、認識、固定観念、レッテル、偏見、差別などの類型化された観念を指す用語である。アメリカのジャーナリストであるウォルター・リップマンによって命名された。
ウィキペディア
先入観、思い込む、その他の単語が並びました。
我々人間は、教育や経験によって、さまざまなことを先読みすることで、難を逃れてきたのだと思います。
これからも、有効な手段だと思います。
ただし、猛烈なスピードで変化を続けている現在を考えると、変化に対応できない者は、自然淘汰される運命にあるのだろうと思います.
時代の変化に対応できない人たち
人間はこうあるべき、旅行はこうあるべき、会社の面接はこうあるべきだ!
そうです、この「〜べきこと」が日本社会の最大のめんどくさいことなのかもしれません。
これまでの経験を重視して、時代の変化に遅れている人たちは、時代に遅れていることにも気づいていないと思います。
日本の産業は、今のところは、過去の遺産(眠っている技術も含めて)が残っているので、当分の間は大丈夫と思いますが、海外の産業に取って代わる、代わったものも数知れずあります。
固定観念という不必要な経験則は、「めんどくさい」だけですよ。
さらに、日本の敎育は、知識の詰め込み、会話できない英語教育、生活に必要のないむずかしい漢字、etcと過去の有識者の固定観念が作った教育を、いまだに引きずってきました。
特に、試験のための教育は、もう、過去のものです。
教育は、学校の名誉のため、指導した先生の評価ため、子供に順番をつけたりするためにあるのではありません。
そして、させられる教育は面白くないし「めんどくさい」だけだと思います。
積極的に自分から知識を習得することは、新しい発見があって本来は楽しいことだと思います。
「あるべき」は、日本人の最大のマイナス点
「あるべき」という言葉は、その人が成功または失敗した時の経験則からきている言葉だと考えます。
しかし、どんどん時代は変化し、経済の流れの変化、さらに、地球環境の変化、海水温や気温の変化、さらに天変地異がある可能性など、我々が生き残って子孫を残すには、環境に適合できなければならないという事実があります。
経験則は、短期的には必要なことですが、時代の変化に対応するには、邪魔になることが多々あります。
人間の過去の重大な失敗をしないためには、「歴史は繰り返される」と言われていますので、過去の歴史は重要なことだと考えます。
ただ、流れが加速している現在の環境下では、個人の経験則が邪魔になる可能性は多々あると考えます。
経験則や理論は環境で変化する
経験は、短期間には有効なことかもしれませんが、環境因子が一つでも変化したら、無効になる可能性が高いものです。
2020年の日本の夏は、人間が使うエネルギーで温室効果ガスであるCO2を大量に排出した結果、人の体温を上回る気温になることが多くなってきました。
冷房の空気は体を冷やすからあまり使わない方が良いと言われてきましたが、ここ最近は、積極的に体温調整に使うように報道されるようになりました。
環境が変化すれば、一つでも因子が変化すれば、これまでの経験則は役に立たないことがあることを知る必要があります。
個人の好き嫌いでも同じことが言えます。
ある人が、小さい頃に食べた時トマトが嫌いになりました。
嫌いという印象だけど、トマトという名前を聞いただけで、鳥肌が立ちます。
その人は、一生、トマトを食べずに過ごします。
その時のトマトは、嫌な味がしたのかもしれませんが、大人になって味覚が変化したり、トマト自体の品種改良があって、おいしくなっているかもしれません。
理論でも同様のことが言えますね!
ニュートンの法則で説明できない理論は、アインシュタインの特殊相対性理論で説明できるようになりました。
理論も、ある環境因子、(この場合は時代の進歩ですが)の時は正しいけれど、因子が変化すると正しいとは言えないのです。
「めんどくさい」と感じる心、何か違うぞ!、違和感を感じるなぁ!ちょっと変じゃないか?
それが、将来、自分たちが生き延びるためには、重要な感性なのかもしれせん。
技術革新という変化
現在の情報の伝達スピードは一瞬で地球の裏側にいる人に到達します。
インターネットという海を跨いだ光ケーブルがその役目をしています。
さらに、近い距離では携帯電話回線が電波で情報をやり取りします。
さまざまな技術革新や制御が、安価な技術で構築できるようになってきています。
この技術革新に追いつけない人たちは、わからないという不安から余計な口出しをして、「めんどくさい」邪魔をします。
未知なるものへの不安や恐怖があるので、仕方がないのかもしれません。
この変化に対応できるのは、古い経験しか理解できない人ではなく、新しい時代を生きる人たちだと考えます。
国や会社、団体は、常日頃から新陳代謝をしながら、新しい環境に対応できるように、新しい人材を入れながら、変化を楽しむくらいであった方が良いのかもしれません。
時代の変化に対応できる世界
固定観念は、生まれ育った環境で作られているものと考えます。
そして、生きてきた時代によって、その人の固定観念も変化していきます。
時代や環境の変化に対応できるのは、固定観念の少ない若者だろうと思います。
政治や経済、そしてさまざまな運営は、どんどん若者を取り入れて新陳代謝を促すようにしなければならない時代だと考えます。
古くなった人は、どんどん新しい人材を入れて、時代に対応できるようにしなければならないと考えます.
国家も同様で、新陳代謝のできていない日本は、世界の新興国から取り残されていくのだろうと危惧しています.
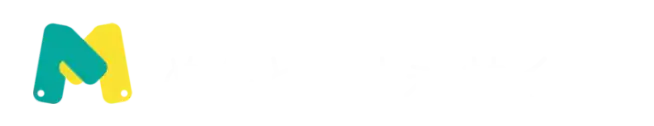


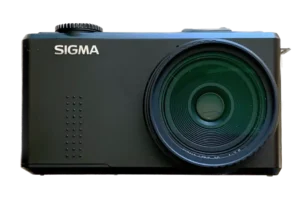









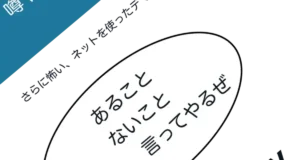






1件のフィードバック
これまでは、動物は環境に適応するために、経験値を元に行動してきました。
しかし、現代の環境の変化は驚くほど速く、数年前の経験値は役に立たないことが多くなってきました。
したがって、固定観念を持たずに、新たなる時代を生き抜くには、できるだけ正確と思われる情報を元に行動すべきと考えます。